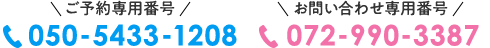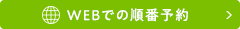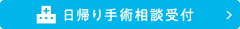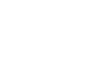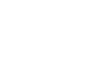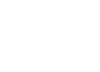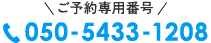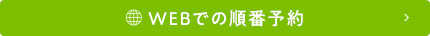日帰り手術は時代の推しか
世界的にエネルギー・原材料価格の高騰が蔓延しており、医療の分野でもその煽りを受け、薬や医療機器・器材の価格が上がっています。物価高に伴う人件費上昇も相まって医療機関の経営は厳しい時代となっており、国立大学病院の赤字も過去最大とのことです。大学病院のような教育病院が事業継続困難な状況に陥れば、医療崩壊に繋がりかねませんのでこの状況を打破する改革案が待たれるところです。診療報酬の改善で赤字補填をという意見もありますが、高齢化の影響等で国の医療費も過去最高を更新している現在、大幅に診療報酬を上げるのも厳しいという見方もあります。
これら病院の赤字や医療費の増大など、昨今の医療経済を取り巻く諸問題は少子高齢化や都市集中型社会といった社会構造に起因していているところが多く、医療の効率化や医療資源の効果的な分配などが解決の糸口になると考えられています。我が国でも2008年より医療費適正化計画として、医療の効率化を軸に医療費削減を目指す施策がすでに実施されておりますが、現状を見るに、役不足な印象は拭えません。日本に限らず、我が国と似た社会構造を持つ諸外国でも同様の問題が起こっており、日本と同じ国民皆保険を導入しているフランスでは、60の施策を柱とする具体的かつ強力な医療費抑制戦略なるものが発表されております。その中身は「無駄を省き、効率化に努める、ただし医療の質は落とさない」という、医療従事者には手厳しい内容のようです。ただ、その施策の中の一つに「日帰り手術の実施向上」というものがあり、時代に即した中身である感も否めません。
日帰り手術は、入院にかかる諸費用の削減の観点から医療費削減に寄与することは言わずもがなですが、リスクの面から躊躇されてきた経緯があります。日本でも日帰り手術は、眼科や外科の一部で比較的積極的に行われてきているものの、その割合は全手術の約22%とも言われており決して多くはありません(アクサ生命調査、2017年)。一方、前述の戦略を発表したフランスではすでに全手術の約64%が日帰りで行われており、この値をさらに80%まで伸ばす目標を掲げています。実はこの数値2013年の43%、2016年の50%を経た上での値ですので、いかにフランスが本気で取り組んでいるのかがわかります。
耳鼻科領域では、日本でもかつては開業医でも鼻(鼻づまり)や耳(耳垂れ)の手術は日帰りで行われてきました。ただ、安全性(出血多量によるショック・コントロール不良のめまい・神経損傷による術後後遺症等)の問題から縮小傾向となり、現在では入院下全身麻酔で行う施設がほとんどです。ただ海外では、保険の違いも相まって積極的に日帰りで同手術が行われてきており、近年はその安全性を裏付ける報告も相次いでおります。一例を示すと、鼻の領域では、複数施設の共同調査で日帰りでの鼻・副鼻腔内視鏡手術の安全性を改めて検証・確認したとの報告(イギリス 2022年)、また耳の領域では耳のメジャー手術(真珠腫性中耳炎、耳小骨再建を伴う慢性中耳炎、並びにアブミ骨の手術)が入院と日帰りの比較において退院後(帰宅後)の安全性に差がなく日帰り手術で十分に対応可能であるという報告(フランス 2021年)が挙がっています。ただ、それらの報告を行った施設は全て、術者を含めて安全性が担保されているということは追記しておきます。
当院でも日帰り手術を2019年の開院以降行っており、現時点で、安全性や治療成績(術後再発や聴力悪化等)の面では、勤務医時代の入院加療で行っていた頃と遜色なく行えております。医療を続けていく上で、多少のマイナートラブルはつきものですが、それを乗り越えて現在も質を落とさず安全で確実な手術を行えているのは、支えてくれているスタッフをはじめ多くの関係者の協力があるからです。改めてここに感謝の意を記します。
日帰り手術の準備完了です
開院当初より日帰り手術目的で来院された患者様に対してはお待たせすることになっておりましたが、ゴールデンウィーク明けより本格的に手術を始動させていただいております。アレルギー性鼻炎に対するレーザー治療等はゴールデンウィーク前より行なっておりましたが、やはり本格的な手術となると手術器具の準備や安全性の管理を慎重に行う必要がありますので時間をとって調整して参りました。
耳鼻科の日帰り手術というのは、今に始まったものではなく明治・大正の時代から耳鼻科開業医でも行われてきた経緯があります。そもそも抗生剤が世に出回る前ですので中耳炎や副鼻腔炎からの髄膜炎・脳炎で命を落とすことも稀でなく、ゆえに感染巣除去や膿を出すため手術が必要であったわけです。当時は現代のような内視鏡や顕微鏡も無く、LEDライトもレントゲンもない状況下で淡い光に裸眼で狭い領域の手術を行っていたわけで、まさしく神業的な手術が行われてきたことになります。一部の匠な術者を除いては中々その神業を体得するのは難しかったようで、手術に伴う後遺症も多く出たことは先人らの報告に記されております。
時代は、明治・大正から昭和・平成を経て令和へと移りました。テクノロジーの発展は医療技術の進歩そのもので、その恩恵を耳鼻科手術領域も受けており、手術による体のダメージをできるだけ減らす「低侵襲化」が進んでおります。耳鼻科領域は骨に囲まれかつバリエーションのある複雑な構造をとっている為、この領域の手術は目的箇所(病変箇所)に安全に到達し、安全に病変除去を行い、安全に帰ってくる(元どおりに戻す)という一連の流れが大切です。手術を安全に行うにあたり手術手技は大事なことですが、それだけでは安全な手術は行えず、いかにアプローチを安全かつ効率的に行えるかが要であり、その為には地図(画像)を読み切ることや裸眼では見えない部分を正確に見せてくれる光(機器)が必要となります。当院では「地図」として胸のレントゲン写真並みの低被曝ながら、耳や鼻の複雑な細部の骨構造を再現しうるCTシステムを導入し、また「光」として有能な顕微鏡・硬性内視鏡システムを用いております。それらのアシストにより、術者の技術を十分発揮しうる、精度の高い日帰り手術ができる体制をとっております。
医療先進国である欧米では国や患者の医療費負担軽減の面からも耳鼻科領域でも日帰り手術は10年以上前から行われてきており、近年はその安全性を評価する報告も多く見受けることができます。「低侵襲化」が実現したからこそ、病院でしかできなかった医療技術をもっと身近にクリニックレベルで、ご希望の方は一度受診の上でご相談ください。