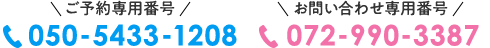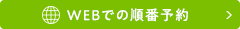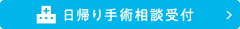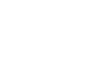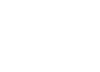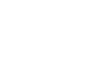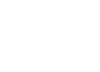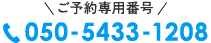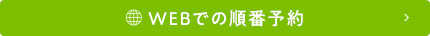まだスギ花粉の季節でないのにアレルギー症状が・・という方を見受けますが季節外れの黄砂の流入があるようで鼻やのどの症状悪化にご留意ください。もちろん寒気の流入の影響か風邪も流行っており、インフルエンザの流行も懸念材料です。欧米でも、昨年末より感染性のインフルエンザA型の変異株が流行しているようで、その感染力の強さから「スーパーインフルエンザ」と呼ばれ警戒されております。変異によって従来のワクチン免疫機構を回避する能力が向上しているという意見もあり国内での感染拡大も心配されるところです。新型コロナの時も変異株が話題になっていましたが、インフルエンザウィルスやコロナウィルスが変異しやすいのには理由があり、それはこれらのウィルスがRNAウィルスだからと言われています。
ウィルスには大きくDNAウィルスとRNAウィルスとがあり、持っている遺伝情報(遺伝物質)がDNAかRNAでその違いがあります。一般的にRNAウィルスは自己複製が不安定で複製時にエラーが起きやすく、ゆえに変異しやすいとされています。対してDNAウィルスは安定的に正確な自己複製ができるため変異が少なく、宿主の免疫機構からも見つかりにくく長期間隠れ続ける能力(潜伏感染)を有する種が多いとされています。ただし長期間の潜伏感染は、のちに宿主(人間)側の免疫機構の弱体化等で自己免疫疾患や癌などを引き起こしうることも知られています。その具体例として、咽頭口腔粘膜に潜伏し続けているEBウィルス(ヘルペスウィルスの仲間)やヒトパピローマウィルスといったDNAウィルスは、いずれも口腔咽頭癌発生のメカニズムに関与が指摘されており、EBウィルスに関しては自己免疫疾患(SLEや多発性硬化症など)をも引き起こすこともわかっています。
ウィルスの語源はラテン語の「毒液」に由来するとのことで、確かにウィルスは感染症だけでなく癌の引き金になったり、免疫を狂わせたりと毒のイメージが強いのも否めません。反転、最近の研究では治療薬としての側面も出てきています。例えば、前述のEBウィルスが作り出すタンパク質に癌を抑制する効果が見出されたり、子供の夏風邪と言われるヘルパンギーナの原因であるエンテロウィルスというRNAウィルスも、長期間潜伏感染する能力を有し癌細胞を溶かす効果が確認されたりと、これらの報告は有望な癌治療戦略に繋がる可能性を示唆しております。人類とウィルスは共生している以上切り離すことはできませんので、ウィルスとの関わりでもたらされる免疫応答の吉凶を正しく理解し、新たな知見を持って臨床に臨み、正しく治療に還元できるようにと思っております。
さて、話は戻して先に述べたインフルエンザの変異ですが、2008-9年にはタミフル耐性変異株が蔓延し薬剤耐性が問題となりました。その影響もあるのか現在WHO(世界保健機関)やCDC(アメリカ疾病予防管理センター)では健常人のインフルエンザ感染でのタミフル等抗ウィルス薬の使用は基本的に必要としないと唱えております。最近では、タミフルの市販薬(OTC)化についての議論が国内からも出ており、市販の検査キットと組み合わせて、OTC化したほうが(対応が)迅速化し早期治療へのアクセスが向上しうること、さらには院内混雑緩和からの二次感染予防にも繋がりえることがOTC化推進の主な理由です。もちろん、使い過ぎによる薬剤耐性や副作用のリスクを鑑みてOTC化に慎重な意見も当然あるので、今後さらに議論が必要かと思われます。因みにニュージランドでは2007年から薬局にて薬剤師面談(処方箋なし)の上でタミフルを供給、5年経過後も特に大きな問題は起きなかったとのことです。世界一のタミフル消費国である日本の医療(制度)を世界の基準に当てはめることに齟齬はありますが、世界の流れにどのように影響されていくのか、今後の動向に注目です。